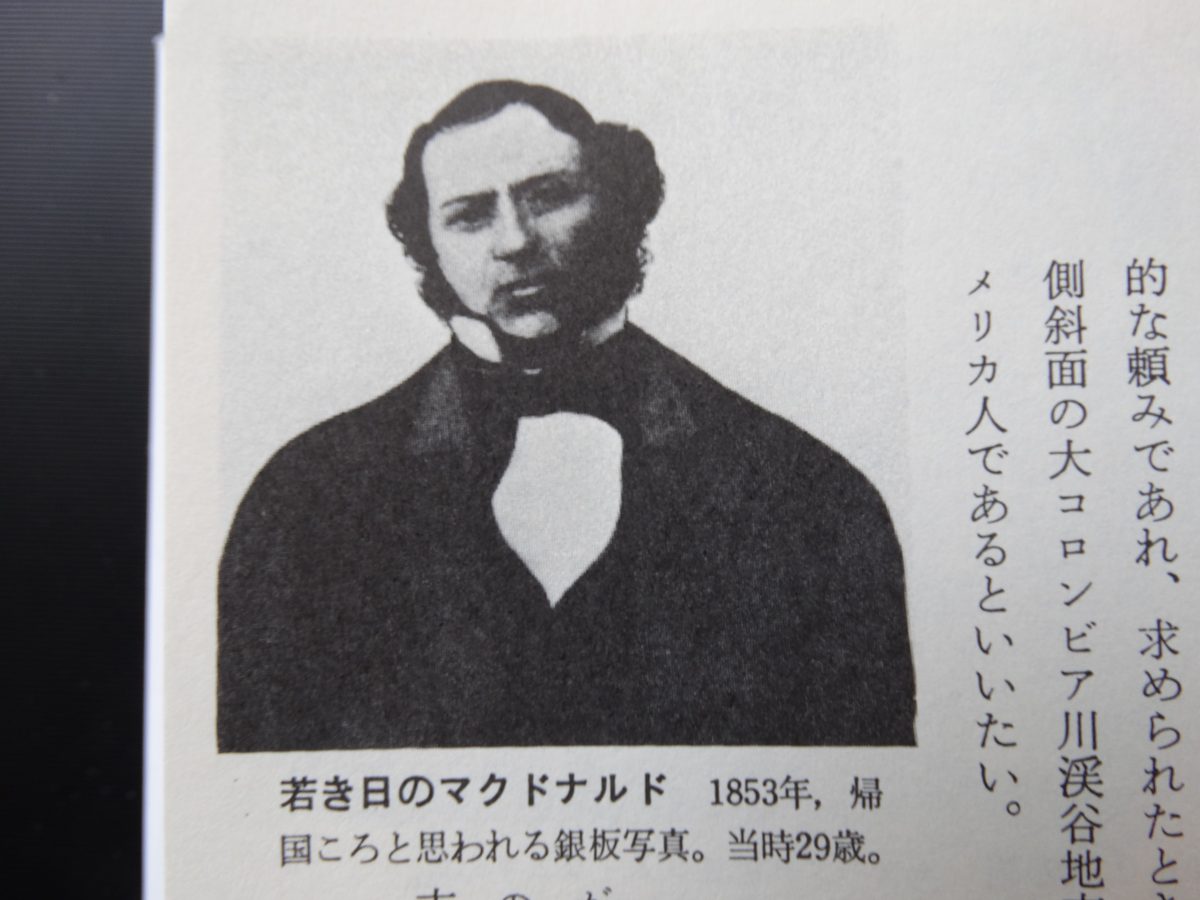焼尻島物語 その12
2026.02.02
焼尻島の水源林と人々の暮らし
編集者:合同会社エゾリンク 安東義乃
北海道・日本海に浮かぶ小さな島、焼尻島。観光地にありがちなにぎやかさとは無縁のこの島には、波と風と、鳥たちの声が響いています。
「何もない。ただ自然があるだけ」
そう言われるこの島で、私は羽幌町観光協会主催の海岸清掃イベントに参加してきました。そこでは、自然と人々の暮らしが静かにつながっているのを感じられ、まるで自然に「入る」のではなく「戻る」ような感覚を味わうことができました。
Contents
島の語り部に聞いた、自然とともにある暮らし
宿泊先の民泊「じぃじの家」を営む、磯野 直(いその すなお) さんから、島の歴史や自然について、じっくりお話を伺いました。
かつて焼尻島はニシン漁で栄えた港町。漁師たちは「地震や大雨、津波のあと、海が豊かになる」ことを知っているそうです。それは単なる迷信ではなく、長年の経験から生まれた知恵なのです。実際、山から海へと流れる土砂には森の栄養が含まれていて、それが海藻を育て、魚を育てます。島の人々にとって「森が海を育てる」という感覚は、暮らしのなかに自然に根づいています。

磯野さんに森をご案内いただきました(写真:行方氏提供)
そんな島の今を支えているのは、明治時代に出された「伐採禁止令」でした。これによって、島の森は守られ、水源林として今日でも島の暮らしを潤し続けています。焼尻島では、水が一度も枯れたことがないというのも、その証です。森に蓄えられた水が湧き水となり、泉や沢から今も流れ出ているのです。ただし、水田をつくるほどの水量はなく、かつての主食はジャガイモ。ふのりやギンナンソウなどの海藻は、今でも食卓には欠かせません。「あるもの」を大切に、身近な自然を取り入れた、足元に根差した暮らしが息づいています。

雲雀ヶ丘公園の池には、たいそう大きな水芭蕉が!
“ない”を嘆かず、“ある”を楽しむ暮らし
磯野さんが出してくれた、バナナの入ったアイスクリーム。なんと、ご近所さんたちと一緒につくったそうです。島では、食べたいときにお目当ての味に出会えるとは限らないアイスクリームですが、「なければ、みんなで作ればいい!」と、たちまち皆で集まって作る楽しい時間になったんだとか。実際作ってみると、ふわふわとした柔らかな食感に皆で感動したそうです。
そんな話を聞きながら、この島では、知恵や工夫を分かち合いながら暮らすことで、人と人との距離が自然と近くなるんだなと感じました。何もないからこそ、心が自由になる。足りないものを探すよりも、今あるものをどう楽しむかに目を向ける。こうした姿勢の中に、私たちが忘れかけている「豊かさ」のヒントがあるように思いました。

「民泊じいじの家」に集っての夕食会(右から筆者、磯野さん)(写真:行方氏ご提供)
子どもは島の宝
フェリーが止まれば、島には入ることも出ることもできません。
そんな“自然まかせ”の暮らしも、島の人にとってはごく普通のこと。
現在、島には6人の子どもたちが暮らしています。年に一度の運動会は大人も巻き込んでの一大イベントだそうで、「島のお祭りなんです」と磯野さんは笑って話してくれました。 そんな磯野さんが、まっすぐに言った言葉 「子どもは島の宝です」。 自然の厳しさと向き合いながら生きる中で、 「海の豊かさを支える森を、みんなで守る」ように、 「島の未来を担う子どもを、みんなで育てる」。 短期的な効率ではなく、長い時間軸で未来を見据えた意識が、この島では自然と育まれているようです。
森のなかで、自然と“対話”する
焼尻島は森も含めて、自転車で走ることができるんです。

森の中も自転車で走れる楽しい小道
私の訪れた6月は、いろんな花の開花期でした。ホオノキの濃厚な香りや見事なエゾカンゾウの群落、控えめだけど凜としたスカシユリが島を楽しく彩っていました。

青空が似合うエゾカンゾウ。虫が花粉を食べてますね~

ホオノキの花。甘い香りに誘われて虫たちが集まっています。
森へと続く小道が島のあちこちにあり、人や自転車、猫たちが自由に行き交っていました。エゾセンニュウの声があちこちで聞こえ、時折ツツドリの「ぽぽっ」という低い声が響くこの島では、人間は決して主役ではなく、生きもの同士が程よい距離感で共に生きてるなという感覚になりました。
島にはヒグマがいないため、森の中でも緊張を解き放ち、自然に身をゆだねることができます。丘を登った先に続く、まっすぐな舗装路。移動の心地よさがある一方で、何も“特別なこと”が起きないようにも見えるんですね。けれども、しばらく立ち止まっていると、変わらないと思っていた風景のなかに、今まで気づかなかったものがふと現れてきました。
アスファルトを横切る小さな虫の姿に気づいたのをきっかけに、巻き貝が残した、透明で光る「小さな道」が網の目のように広がっていることに目が留まりました。

たくさんの白い貝と貝が歩いた道
気の向くままに視点を変え、感じたままに自然に惹かれる。ここではそれが、どこまでも許されているのです。視界を遮る障害物もなければ、思考を中断させる騒音もない。静けさと余白が、感性をほどいてくれる瞬間が何度も訪れました。
滞在すること自体が“環境教育”
焼尻島で出会った方々から、「楽しんだ分、島に貢献したくなるんです」という声をよく耳にしました。
この島の水と森、そして人々との距離感は、自然を“征服”するのでも、“管理”するのでもなく、あるがままを受け入れてともに暮らすというもの。そうした関係性が、自分もこの自然の一部だという気づきをもたらし、気づけば「何かを返したくなる」気持ちへと変わっていく...滞在すること自体が、学びとなり行動につながっていく—それはまさに、“究極の環境教育”ではないでしょうか。
実際、夕日が海に沈む光景を見ながら、こみ上げた感情は「ありがとう~!」でした。
島の未来、私たちの未来
隣り合う焼尻島と天売島。海を挟んですぐ近くにあるふたつの島でも、その進み方は大きく異なっています。焼尻島は静けさと水源林を、天売島は海鳥との共生を選んできました。

坂道を上ると見えてきた天売島
天売島で生まれ、今は焼尻島で暮らす磯野さんの話を聞きながら思ったのは、それぞれが土地の歴史と風土に根ざして歩んでいるんだなということ。どちらが正しいかではなく、自然と人との関係に“ひとつの答え”はないのだということ。
磯野さんは、ふとした会話のなかで「カラスが最近減っているんです」と語りました。
「珍しい生き物がいなくなるより、当たり前にいた生きものが姿を消すことの方がずっと怖い」と。ほんの小さな変化に気づけるかどうか。その感性こそ、自然の厳しさと向き合いながら暮らしてきた人の知恵なのだと思います。そうした言葉に耳を傾けることは、島の未来、私たちの未来を見つめるヒントになると感じました。
「余白」が教えてくれる本当の豊かさ
島を訪れた人々は口々に言います。
「また来たくなる」「“何もない”ことを満喫している」「この静けさがたまらない」
人によって、感じ方はさまざま。でもそのどれもが、この島が持つ「余白」の力を語っています。なにかを詰め込むのではなく、なにもしない時間の中で、自分の感覚がふっとひらかれる。焼尻島は、そんな時間をくれる場所でした。
心が満たされる島
訪れたあとも、あの静けさは心に残り続けています。ふとした瞬間に、あの鳥の声や、夕日の色がよみがえって。そして、また行きたくなるんです。派手さや便利さでは語れない“本質的な魅力”。あなたにも体感してほしい。

本活動のご支援について
北海道、北海道コカ・コーラボトリング(株)、(公財)北海道環境財団の三者による協働事業「北海道e-水プロジェクト」の助成を受けて作成しています。
羽幌町と包括連携協定を締結している日本生命保険相互会社旭川支社さまからご支援をいただいています。同社が全国で展開しているサステナビリティ活動「一緒に未来を育てよう。にっせーのせ!ニッセイサステナプロジェクト」の一環としてのご協力です。

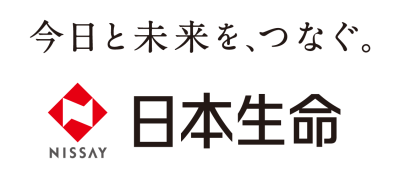

安東 義乃
- 合同会社エゾリンク 代表
- 他の記事
京都大学大学院にて理学博士を取得。現在は北海道大学の研究員として在籍しながら、同大学の研究員仲間とともに、北大発認定スタートアップ企業「合同会社エゾリンク」を設立。大学の総合知を、専門人材を介して社会へ還元する取り組みに力を注いでいる。
事業内容:環境教育コンテンツの開発、大学研究成果の社会実装支援、博士人材の育成支援、地域ESD拠点としての活動
公式ウェブサイト:https://sites.google.com/view/ezolink/